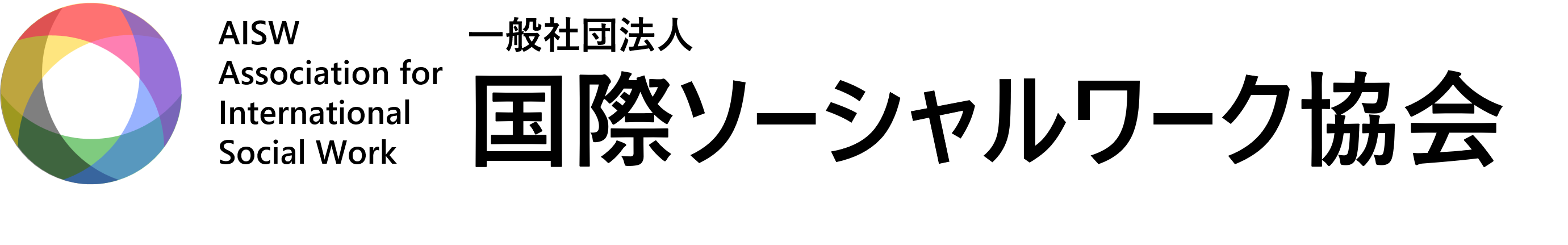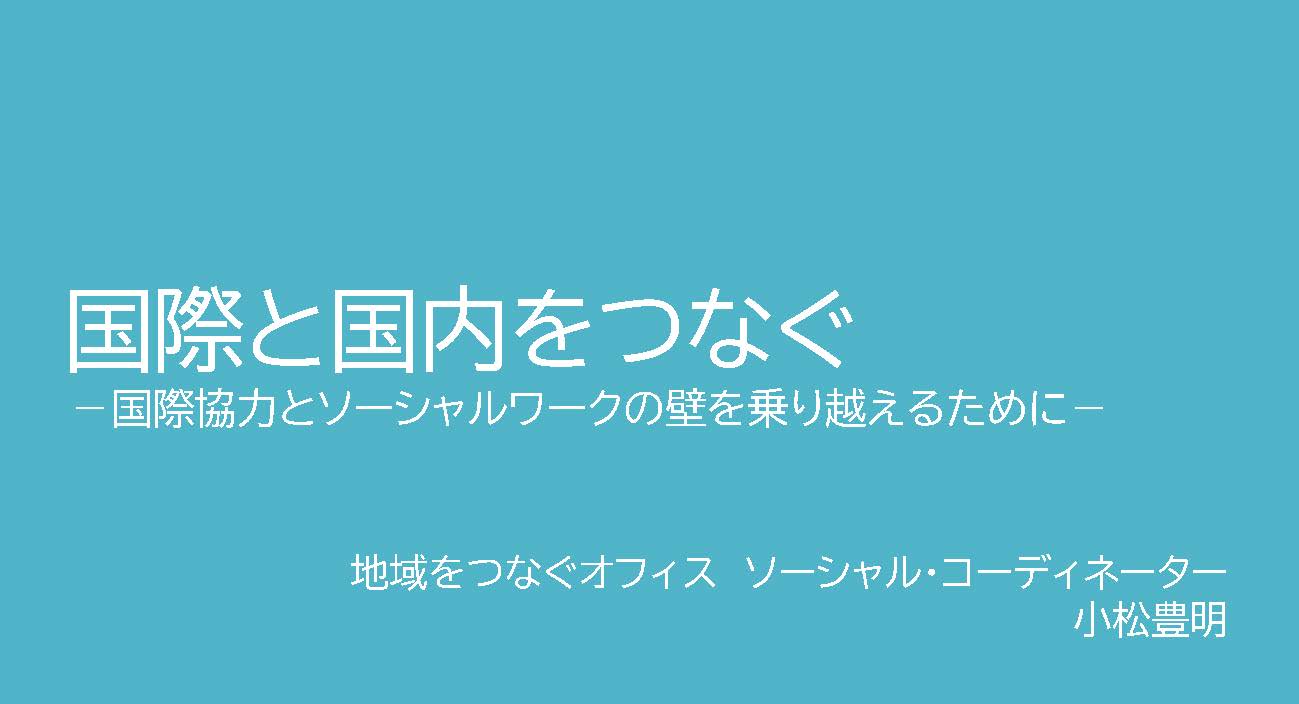主題講演 小松豊明氏「国際と国内をつなぐ:国際協力とソーシャルワークの壁を乗り越えるために」 資料
2025年5月24日、日本女子大学にて国際ソーシャルワーク協会主催、小松豊明氏 講演会「国際と国内をつなぐ:国際協力とソーシャルワークの壁を乗り越える」が開催されました。主題講演である小松氏の当日配布資料をご本人の了承のもと下記掲載いたします。
国際と国内をつなぐ-1「国際と国内とつなぐ:国際協力とソーシャルワークの壁を乗り越えるために」講評 ヴィラーグ ヴィクトル(日本社会事業大学)
小松豊明氏による「国際と国内とつなぐ:国際協力とソーシャルワークの壁を乗り越えるために」をテーマとした講演を、大きく導入編・理論編・調査編に分けることができる。
導入編で紹介された演者の国際的な実践活動が、ソーシャルワークの旧国際定義における「過程」という考え方と強く関連している。具体的には、実践におけるプロセスの重視こそ、効果的な国際協力につながるという考え方である。つまり、ローカルな文化や知、ローカルな人々との付き合い、即ちパートナーシップの上で実践が成り立っている。このようなパートナーシップ関係の上で、現地の人々の国際協力プロジェクトに対するオーナーシップが生まれる。これは、本当の意味での自立とプロジェクト効果の持続性に結び付く。日本の社会福祉実践・ソーシャルワーク実践では不十分な場合もあるため、講演から見習うべき主要な点の一つである。
理論編では、国際開発とソーシャルワークのギャップと接点は何かという問いについて先行研究を基に整理された。様々な比較表をみる限り、本質的な違いを感じさせる要素があまりなく、むしろ認識のずれという印象を受ける。但し、ソーシャルワーカーのアイデンティティをもっていない人の実践を、ソーシャルワーク側が一方的にソーシャルワークと名付ける必要があるかどうか、そもそもの疑問が残る。その背景には、分野間だけでなく、研究者と実践者の間の認識のずれもあるかもしれない。しかし、両分野が相互に学び合うことがたくさんあることは確実である。その架け橋となれるものとして、演者の実践及び研究活動を位置づけることができる。
調査編では、実践者とのインタビューから多くの示唆が得られた。ソーシャルワークが国際開発から最も学ばないといけないことは、前述のようにコミュニティとの付き合い方である。実践が他国で行われている以上、実践者が必然的に「よその人」という立場に置かれてしまうことがその根本にある。結局は、支援者でありながらも「外国の人」に当たるため、その国の法制度はもちろん、現地の文化などに従わなければならない。一方、国境を越えない国内のソーシャルワーク実践の場合、地域社会の人々とのパワー関係の中で、パターナリスティックな実践になりやすい。本来ならば、国内外を問わず、コミュニティや人々と実践者の間に上述のように対等な関係があって初めてコミュニティのニーズを把握でき、初めて真のエンパワメントが実現される。その中で、先述のようなオーナーシップがコミュニティの自立の前提であり、関われる援助期間を意識した、終わりが見える支援が成立する。そのために、コミュニティのリーダー育成やコミュニティ全体の底上げは、国内でも必須である。
他にもインタビュー調査から浮き彫りになった点として、ソーシャルワーカー自身も、そして開発援助者も、ソーシャルワークを研究者やグローバル定義よりも狭義に捉えていることが伺える。特に、個人を対象とした個別支援のイメージが強く、ミクロでしかソーシャルワークが捉えられてないことがもったいない。但し、近年の政策動向からも個別援助しかできないソーシャルワーカーはもう要らないという強いメッセージが伝わってくる。新しい養成カリキュラムをみてもメゾ・マクロ実践もできるようなソーシャルワーカーは国内でもますます期待されている。また、地域共生社会の実現に貢献できる、個人だけではなく地域社会全体を視野に実践が展開されるソーシャルワークが求められている。とりわけ、国内でもコミュニティソーシャルワーカーの役割である。しかし、住民を巻き込む力だけでは不十分で、国際協力における能力向上などのように、住民に力をつけることにも同時に取り組む必要がある。これが欠けてしまうと、コミュニティの機能が発揮されず、単なる安上がり福祉のための住民への丸投げになってしまう。この点は、無縁社会やコミュニティの崩壊が進んでいる現代においては極めて重要な教訓である。
以上のように、小松氏の講演全体を通して、国際ソーシャルワーク協会が目指そうとしている活動の本質に迫るような示唆を多く得ることができた。この場をお借りして、本協会を代表して改めてお礼を申し上げる。